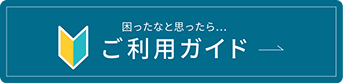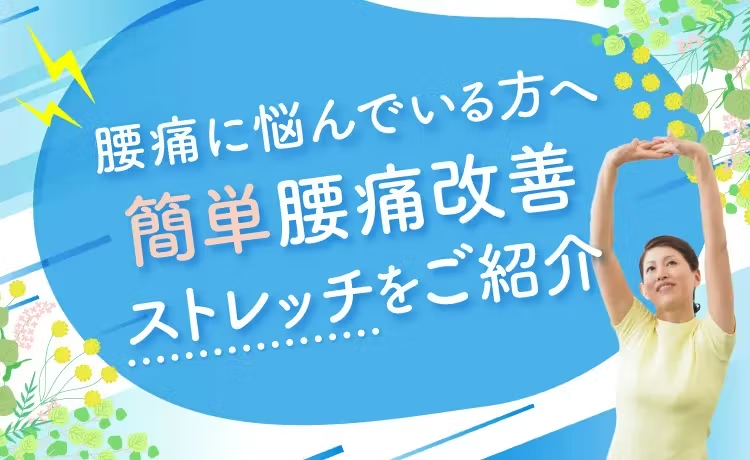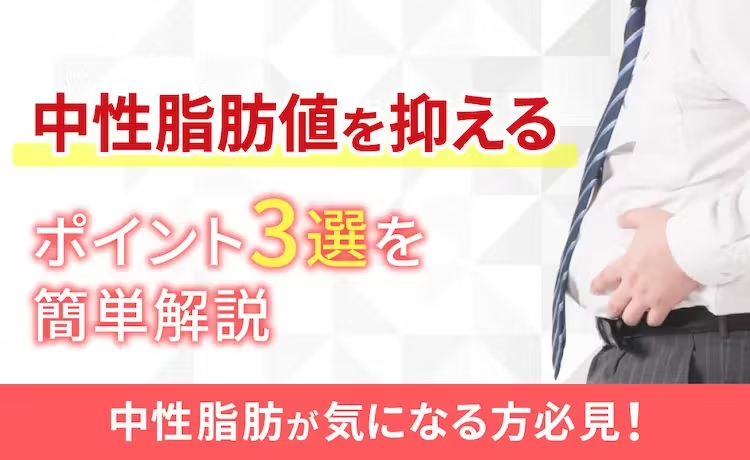脂肪の一種である中性脂肪は、エネルギー源や体温維持、臓器の保護など、生命活動において重要な役割を果たしています。しかし、中性脂肪が多すぎる、減らすことができていない、となると肥満やドロドロ血液の原因となるなど、健康に影響を及ぼす場合があります。
この記事では、中性脂肪の概要や基準値について紹介し、中性脂肪値を抑える上での3つのポイントを説明します。
<中性脂肪値を抑える3つのポイント>
1.中性脂肪値を抑えるために、まず自分の適性を知ろう
2.中性脂肪値を抑えるための食生活ポイント
3.中性脂肪値を抑えるための運動のポイント
中性脂肪の正しい知識を身に着け、健康づくりに役立てましょう。
01中性脂肪は多いとなぜ良くない?

中性脂肪はエネルギー源になるほか、体温を適温に保ったり、臓器を保護したりと、健康を維持するために重要な役割を果たしていますが、増えすぎると肥満やドロドロ血液などの健康リスクを引き起こす原因になってしまいます。
生命活動を維持するための主なエネルギー源は、ごはん・パンなどの主食や果物などに含まれるブドウ糖です。ブドウ糖は体内にためておけないため、毎日の食事からとる必要があります。体内の中性脂肪はブドウ糖の不足を補う形で利用されます。しかし、ブドウ糖の摂取量や体内の中性脂肪が多すぎるなどの理由で消費されなかった余分な中性脂肪は、血液中を流れて脂肪組織・肝臓・皮膚の下に蓄積され、肥満の原因となります。さらに、血液中にも蓄積されるため、いわゆるドロドロ血液となり健康リスクが高まります。※1
血液中の中性脂肪は、大きく分けて「外因性トリグリセリド」と「内因性トリグリセリド」の2種類があります。
- 外因性トリグリセリド
- 食べ物に含まれる脂肪が腸に吸収され血液中に排出されたもの
- 内因性トリグリセリド
- いったん肝臓に吸収された脂肪が後から血液中に排出されたもの

中性脂肪が多くなる原因として考えやすいのは、脂質の多い食べ物やアルコールの過剰摂取ですが、病気が潜んでいる場合もあります。糖尿病で血糖値が高くなると、体内で余った糖分を使って肝臓が中性脂肪を作り出すので血液中の中性脂肪が増加する場合があります。中性脂肪の数値は健康のバロメーターともいえるので、数値が高い場合は基準値まで減らすための対処が必要です。
02中性脂肪の数値

中性脂肪の数値は、健康状態を判断するうえで重要なデータであり、健康診断などの血液検査から数値を知ることができます。健康に問題のない人の中性脂肪の基準値は、空腹時で30〜149mg/dl(デシリットル)です。※2
食後は中性脂肪値が増加するので、正確な値を計測するためには、検査の約10時間前から、水以外の飲み物や食べ物を摂取せずに血液検査を実施します。※3
健康に問題がなくても体質などの影響で、中性脂肪の数値が高めに出る人もいますが、基準値を上回っている場合は、生活習慣を改善しましょう。
03中性脂肪値の抑え方

中性脂肪の数値が高くても、自分の適性を理解したうえで、食事・運動を中心に生活習慣を改善することで、中性脂肪値を抑えることが期待できます。
まずは「自分の身体の状態を把握できているか」「食べすぎていないか」「運動不足になっていないか」など、日々の生活を振り返り、改善することで、中性脂肪値を知らず知らずのうちに数値を高めてしまうような行動を減らしていきましょう。
中性脂肪値を抑えるための具体的な方法やコツは、これから詳しく解説しますので、中性脂肪が気になる方はぜひ参考にしてください。
04中性脂肪値を抑えるために、
まず自分の適性を知ろう

中性脂肪対策で最初にすべきことは、自分の適正体重と1日に必要なエネルギー量を把握することです。適正体重は「身長(m) × 身長(m)× 22 = 適正体重」の計算式で求められます。
- 計算例
- 身長160cmの場合は、1.6 x 1.6 x 22 = 56.32 となりますので、適正体重は、約56.3kgです。
1日に必要なエネルギー量は、基礎代謝量と身体活動レベルによって異なり、一概に説明することは難しいものです。日本医師会のホームページでは目安のエネルギー量を調べられるので、より詳しく知りたい方は下記リンクよりチェックしましょう。※4
自分の適正体重と1日に必要なエネルギー量の目安を把握したうえで、「適正体重を超えているから運動と食事で体重を落とす」「必要以上にカロリーを摂取しているから食事量を減らす」など、食生活や運動の見直しにつなげるのが重要です。
05中性脂肪値を抑えるための
食生活ポイント

中性脂肪値を抑えるための食生活のポイントについて、やるべきこと・やってはいけないことを解説します。
やるべきこと
脂質の量をコントロールする

食事に含まれる脂質の量は、同じ食材を使っていたとしても、料理で使う油の量が増えるほど多くなります。料理方法で見ると「焼く→炒める→揚げる」と右に行くほど多くの油を使い、脂質量も増加します。揚げ物よりも焼き料理を多く食べるよう意識し、脂質のとりすぎを防ぎましょう。
中性脂肪値を抑えられる食材を選ぶ

中性脂肪値を抑えられる食材として、代表的なものを紹介します。
- 魚介類
- 魚に含まれる良質な油である「DHA」や「EPA」には、中性脂肪値を抑えるといった効果が期待できます。中性脂肪対策として、魚中心の食生活を意識するとよいでしょう。※5
- 海藻・きのこ・野菜など食物繊維が豊富な食材
- 食物繊維は、中性脂肪が腸内で吸収されるのを防ぐ働きがあります。特に、野菜・海藻・豆類に豊富に含まれる水溶性の食物繊維は、脂質の一種である「コレステロール」を減らす働きを持ち、一石二鳥です。※6
- 大豆など植物性たんぱく質が豊富な食材
- 植物性たんぱく質は、中性脂肪やコレステロールの数値を抑える作用があります。特に納豆は、健康な血管づくりをサポートする食材として有名です。※7
和食をメインにする

洋食は、肉がメインの料理が多く、バター・油をたっぷり使用するため、中性脂肪が増える原因となります。和食は、脂質や糖分が少なく、魚介類・野菜・大豆など中性脂肪の吸収を防ぐ食材を多く使用します。
和食中心のメニューにすることで、中性脂肪値を抑えられるでしょう。
やってはいけないこと
過度な糖質制限

中性脂肪値を抑えるために、極端な糖質制限をすることは避けましょう。糖質が不足しすぎると、活動に必要なエネルギーが足りなくなったり、意識障害の原因となったりします。
糖質をとりすぎると中性脂肪の増加につながることは事実ですが、糖分は身体にとって必要なエネルギー源です。極端に減らすのではなく、適度な量をとるのが重要です。
油や脂質を一切とらない

油や脂質を一切とらない食生活は、健康によくありません。飽和脂肪酸を多く含むバターやマーガリン、パーム油などを避け、オリーブ油やえごま油、青魚に含まれる脂を取るように心がけましょう。中性脂肪値の上昇を抑える効果が期待される油も発売されていますので活用してみるのも良いでしょう。
06中性脂肪値を抑えるための
運動のポイント

糖質・脂質はエネルギー量が多いため、食事でとった分を消費しきれていないと、中性脂肪の値が上昇する原因となります。中性脂肪値を抑えるには、脂質・糖質をとりすぎないよう食生活を見直すことはもちろん、運動してエネルギーを消費することも大切です。
運動する習慣をつけると、血流がスムーズになり、しなやかで健康な血管を維持できることが期待されます。
日常生活から取り組む
これまで身体を動かす習慣がなかった人でも、日常生活で簡単にできる運動のポイントを解説します。
ウォーキングする

有酸素運動は中性脂肪値を抑えるのに有効だといわれています。特におすすめなのは、簡単に始められて継続しやすいウォーキングです。時間・場所を選ばずマイペースで続けられるため、普段運動をしない人でも、取り入れやすい運動です。
ウォーキングのポイントは、姿勢と歩行速度です。
- 姿勢
- あごを引き胸を張ることを意識します。肘は90度に曲げ、前と後ろに大きく振りながら歩きましょう。
- 歩行速度
- 歩く速度は普段歩いている時と同じか、それよりも速いくらいがおすすめです。
階段を使う

階段の上り下りは平坦な道を歩くのと比べ、筋肉をたくさん使い、エネルギー消費量も多いので、効果的だといえます。
厚生労働省は、健診結果が基準範囲内の18〜64歳の人に対し「3メッツ以上の運動強度を毎日60分実施する」ようすすめています。身体活動とは、仕事・家事・通勤などの生活運動とスポーツなどの運動を合わせたものを指します。
階段を下りる動作の運動強度は3.5メッツ、上る動作は4.0メッツにあたります。
有酸素運動と筋トレを組み合わせて行う
有酸素運動は中性脂肪対策の基本です。中性脂肪値を抑えるにはエネルギーを消費する必要があり、ウォーキング・ランニング・サイクリング・水泳といった有酸素運動は、効果的にエネルギーを消費できます。
より効果を高めるには、有酸素運動の前に無酸素運動である筋トレを取り入れるのがおすすめです。筋トレは、脂肪分解作用のある成長ホルモンの分泌を促し、基礎代謝を高め、有酸素運動によるエネルギー消費量を増やします。※8
有酸素運動と筋トレそれぞれのポイントを解説します。
有酸素運動のポイント

有酸素運動は、スタートから約20分後に脂肪がエネルギーとして燃焼する効果が高まります。中性脂肪値を抑えるには、1日30分以上&週3回以上の有酸素運動を継続するのが理想です。
しかし、連続して20分運動しないと脂肪が燃焼しないわけではありません。5分、10分の有酸素運動でも脂肪は燃焼するので、短時間でも積み重ねて合計20分以上になるようコツコツ運動しましょう。
筋トレのポイント

運動の習慣がない人が無理をすると、身体を痛めてしまう場合があります。特別な器具を使って、ハードなトレーニングをする必要はありません。まずは軽いストレッチから始め身体を動かすことに慣れ、少しずつ筋トレを取り入れて、だんだん運動強度をあげていきましょう。
大きな筋肉を鍛えると、基礎代謝がアップして脂肪燃焼効果を実感しやすくなります。大きな筋肉は、太もも前部の「大腿四頭筋(だいたいしとうきん)」やお尻の「大殿筋(だいでんきん)」など下半身に集中しています。そのため、スクワットをはじめとする下半身をターゲットにした筋トレをすると効果的です。
07まとめ

中性脂肪は、脂肪の一種で生命活動のためのエネルギー源にくわえ、体温維持や臓器の保護といった大切な役割を果たしています。しかし、中性脂肪値が過剰だと、肥満やドロドロ血液など、健康に悪影響を及ぼす可能性があります。
健康な人の空腹時の中性脂肪の基準値は、30〜149mg/dlです。基準値を超えている場合は、食事や運動を改善して中性脂肪値を抑えることを目指しましょう。※2
食事のポイントとして、油・脂質を控える、中性脂肪値を抑える働きのある食材を積極的にとるなどが挙げられます。運動のポイントは、ウォーキングや階段の上り下りなど日常生活のなかで身体を動かす酸素運動と、無酸素運動である筋トレを組み合わせることです。運動を習慣化することで中性脂肪値を抑えることに加え、しなやかで健康的な血管を維持することにもつながります。肥満やドロドロ血液などの健康リスクを減らすためにも、生活習慣を見直し中性脂肪値を高めてしまうような行動を減らしていきましょう。
参考
※1 大正製薬ダイレクト
※2 東邦大学医療センター
※3 仙台駅前 内科・糖尿病クリニック
※4 日本医師会
※5 ニッスイ
※6 健康長寿ネット
※7 JCVN-医学ボランティア会
※8 横浜市スポーツ医科学センター
この記事の監修者

武井智昭
慶應義塾大学医学部卒業後、一般内科、小児科、感染症、アレルギーの医師として立川共済病院、平塚共済病院小児科医長、北里大学北里研究所病原微生物分子疫学教室、横浜市内のクリニック副院長、小谷クリニック内科・小児科(訪問診療部)部長、なごみクリニック内科・小児科・アレルギー科院長を経て2020年より高座渋谷つばさクリニック院長を務める。
高座渋谷つばさクリニック


 スキンケア
スキンケア
 オールインワンジェル
オールインワンジェル
 洗顔・クレンジング
洗顔・クレンジング
 化粧水
化粧水
 スペシャルケア
スペシャルケア
 メイク
メイク
 ボディ&ヘアケア
ボディ&ヘアケア
 ヘルスケア
ヘルスケア
 美容・健康グッズ
美容・健康グッズ
 暮らしの雑貨
暮らしの雑貨
 すべての商品
すべての商品