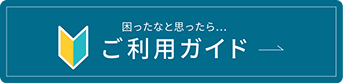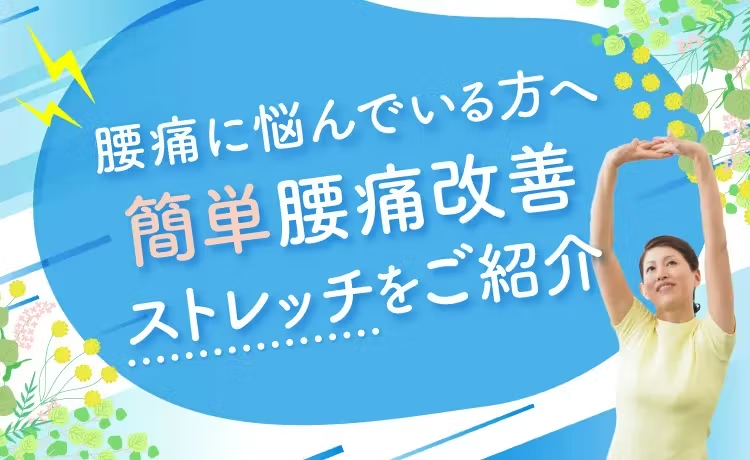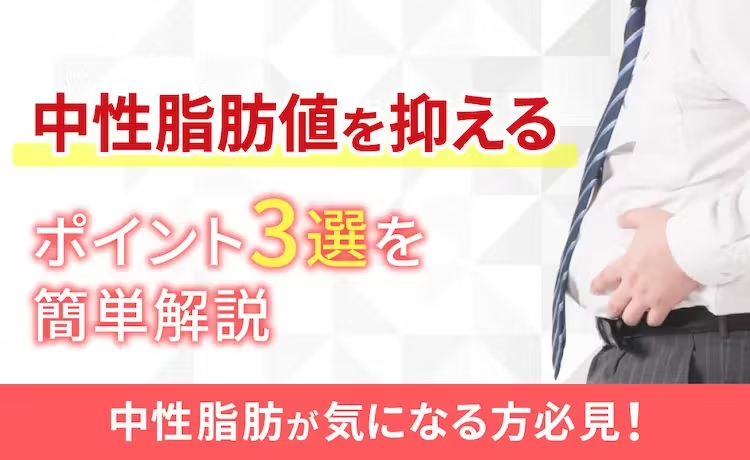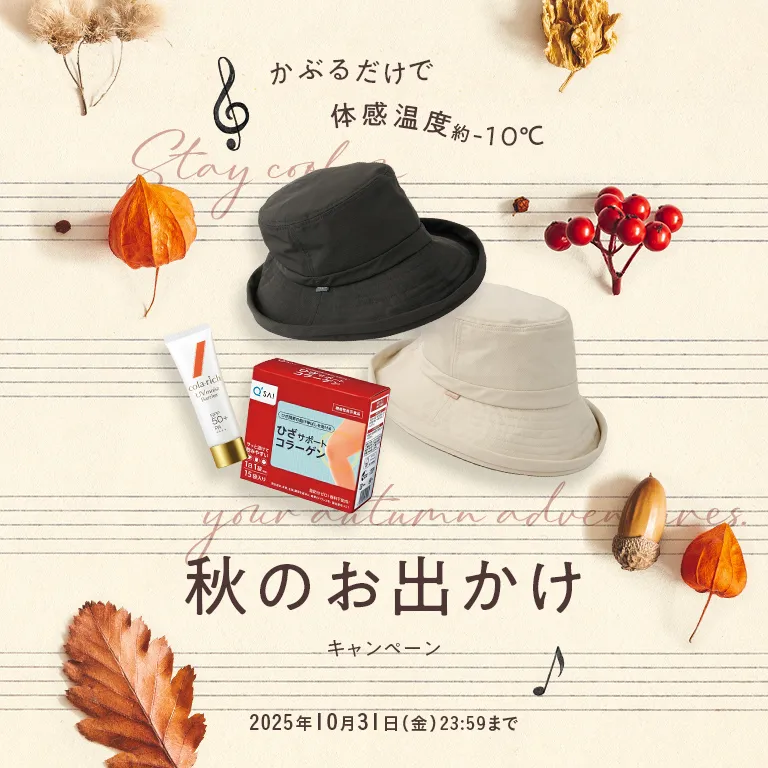「1日1回便が出ない=便秘」といった知識は誤った知識で、便の状態を判断してしまう人も少なくありません。また、快便かそうでないかは、健康かどうかを知るうえで大切な確認ポイントです。便の状態をチェックすることで、健康管理がしやすくなります。
この記事では、快便の定義や、便秘や快便対策に関するよくある思い込み、便の状態で確認すべき項目を紹介します。快便度をしっかりチェックして、健やかな毎日を送りましょう。
01快便とは?

快便とは、「すっきりと便を出すことができる」ことです。たとえ毎日便が出ていなくても、無理をせずにスムーズに排便でき、お腹の張りや痛み、残便感がなく、すっきりしていれば、快便であるといえます。
逆に、毎日排便していたとしても、強くいきまないと出てこない、残便感があるといった場合には、快便とはいえません。
1日1回排便しなければ「お腹が張って不快感がある」と感じる人もいれば、数日間排便がなくても「問題なくすっきり快適」という人もいます。感じ方は人それぞれ異なるため、排便の頻度や便の量にとらわれず「便の悩みがないか」で快便かどうかを見極めましょう。
02便秘だ!と勘違いしやすいケースと誤った便秘対策

便秘などで調子が悪いと思い込んでいても、実は問題のないケースも少なくありません。
ここでは、お通じの不調と間違って思い込んでしまっていたり、誤った対策をしてしまっていたりするケースについて確認してみましょう。

1.毎日便が出ないと便秘である

「1日1回便が出ない=便秘である」と思われがちですが、実は便秘かどうかは排便の頻度で決まるわけではありません。
「慢性便秘症診療ガイドライン 2017」では、便秘を下記の通り定義しています。
・本来体外に排出すべき糞便を十分量かつ快適に排出できない状態
数日に1回の排便であっても、量が少なすぎたり、苦痛を伴ったりせずにスムーズに便が出るのであれば、便秘とはいえません。

2.便の量は多い方が良い

便の量が多いほど良いわけではありません。「本来排便されるべき量」がしっかり出ているのであれば、快便といえます。
便の量は食事内容によって変わってきますが、1日あたり100g~200gが目安です。ただ、量ではなく、排便後に違和感がなく、すっきりしているかが最も重要です。便が多く出ていても、お腹の張りや残便感がある場合は、便秘かもしれません。

3.便秘の時には力んで便を出すと良い

毎日コンスタントに排便した方が身体に良いという思い込みから、力んで無理に排便している人も少なくありません。ですが、まだタイミングが来ていない状態で力んで排便すると肛門に負荷がかかり、痔(じ)に繋がる恐れがあります。
また、排便の姿勢自体が肛門にとっては負担になるので、長時間トイレで力むことは避けましょう。3分ほど排便を試みても出てこなければ、一旦諦めてトイレを出ましょう。

4.目覚めに1杯の水を飲むと快便になる

昔から知られている便秘対策として、目覚めに1杯の水を飲むという方法があります。確かに水を飲むと、水分の重さによって腸が刺激を受け、腸が活発に動き出します。しかし、飲む際には水の温度に気をつけましょう。
冷たい水を飲むことで腸が冷え、かえって腸の動きが鈍ってしまう場合もあります。常温の水やぬるま湯などの温かいものであれば、腸を冷やさずに刺激できるのでおすすめです。

5.食物繊維を多く食べると快便になる

食物繊維が便秘対策に良いというイメージがありますが、逆効果の場合があります。食物繊維は、腸の中で水分を吸収し膨らむ性質があり、便に含まれる水分を増加させて便の体積を大きくし、排便をサポートします。
しかし、ストレスで胃腸が弱っている場合には、消化器系が弱っているため、食物繊維を消化する際の負担が大きくなります。そのため食物繊維を多く摂取しても、効果が少ないだけでなく、かえって消化器に悪影響を与えてしまう場合もあります。
胃腸の調子が悪い時は、食物繊維を控えて、ごはんやうどんなど水分を多く含む炭水化物を摂ることもおすすめです。炭水化物は消化しやすく、便の量を増やして排便を促す働きがあります。

6.便秘薬は便秘解消に効果的である

便秘に悩んだ際、便秘薬に頼る人も多いかと思います。しかし、ストレスが原因の便秘の場合、薬によっては悪影響を与えてしまう場合があります。便秘薬を使用すること自体は誤った対策ではありませんが、選び方にはご注意ください。
ストレスが原因の便秘は、自律神経の乱れにより大腸の動きが活発になりすぎています。そこで腸の動きを活性化する便秘薬を服用すると、腸に余計な負担を与えてしまいます。ストレスが原因の場合には、整腸剤がおすすめです。便秘の原因に応じて、適切な薬を選びましょう。
理想は便秘薬に頼りすぎず、食生活を整えて腸内環境を改善する、適度な運動をする、好きなことをしてストレスを解消するなど根本的な生活習慣の改善を行うことです。
03理想の便のポイントとは?
自分の便をチェックしよう

「理想の便」とはどのような状態でしょうか。便のコンディションは、あなたの心と身体の健康を表しています。
健康管理のために、ぜひ毎日の便の状態を確認する習慣をつけましょう。
硬さ(形状)・量・色・におい、4つのチェック方法を紹介します。
1.硬さ(形状)をチェックする
便の状態の良しあしは、硬さ(形状)に注目するとわかりやすいです。便の硬さ(形状)を確認する目安として「ブリストル便形状スケール」が国際的に使われています。
ブリストル便形状スケールは、英国ブリストル大学のHeaton博士が1997年に提唱した指標で、便の形状と硬さを7段階に分類したもので、便秘や下痢の診断にも利用されています。
便の硬さ(形状)は、便に含まれる水分量で変わります。理想的な便は硬すぎず、柔らかすぎない便です。水分の割合は7〜8割程度になります。
水分の割合が6割を下回ると、うさぎの糞のような硬くてコロコロした便になり、便秘の状態といえます。水分の割合が9割を超える場合、柔らかく泥や液体のような便になり、下痢の状態となってしまいます。

2.量をチェックする
食事の内容にもよりますが、1回あたりの理想的な排便量は約150g〜200gとされています。便の重さを測ることは現実的ではないので、サイズに換算すると、「すっきりと排便できた」と感じる快便時の便は、長さ10cm大かそれ以上の大きさです。
1回あたりの排便で、およそバナナ1本と同じかそれ以上のサイズであれば、コンディションは理想的といえるでしょう。
バナナを目安にすることがわかりにくい場合には、手の長さと比べる方法がおすすめです。手首のシワから指先までの長さの平均は約18cmです。排便後に便の状態を確認できる場合は手をかざしてみて、便の長さが手の長さの半分から同じくらいであれば、理想的といえます。

3.色をチェックする
理想の便の色は、黄土色から茶色です。この場合、大腸内の善玉菌が活発な状態といえます。善玉菌が活発になると、大腸内は弱酸性になります。その結果、胆汁の分泌が抑制され、便の色が黄色っぽくなります。逆に、悪玉菌の勢いが活発になると、大腸内は弱アルカリ性になり、色が黒ずんでしまうのです。腸内環境を整えて、理想の便の色を目指しましょう。

以下の色の便が出た場合には、病気の可能性もあるのでご注意ください。
-
- 白・灰色
- 胆汁の出が悪い時の色です。脂肪のとりすぎによる消化不良や病気の可能性もあります。ただし、バリウムを飲んだ後であれば問題ありません。
-
- 黒色
- 胃腸から出血している可能性があります。イカ墨料理、ビスマス剤、鉄剤、薬用炭 によるものの場合は特に問題ありません。
-
- 赤色
- 肛門に近い部位で出血している時の色です。痔による出血のほか、腸の病気が隠れている可能性もあります。
4.においをチェックする

便のにおいは、腸内細菌のバランスによって変化します。便臭はあるが、きつい悪臭ではないにおいが理想的と言われています。
便のにおいのもとは、「スカトール」「インドール」という物質です。腸内細菌のうち悪玉菌が、肉などのたんぱく質や脂質を分解して発生します。
肉や脂っこい食事を多く食べ腸内環境が悪化すると、悪玉菌が増殖してスカトールとインドールの量が増え、においがきつくなります。逆に、発酵食品や食物繊維、オリゴ糖の多い食事を多く食べると善玉菌が増え、においは抑えられます。 さらに快便にも繋がります。食事のバランスに気をつけ、理想的なにおいの便を目指しましょう。
04まとめ

快便の定義は、毎日多くの便が出ることではなく、快適に排便できてお腹にすっきり感があることです。
便秘や快便対策へのよくある思い込みとして「1日1回便が出ないと便秘」「たくさん便が出るのが快便」「便秘の時には力んで便を出すと良い」などがあります。さらに、対策の中には逆効果になりかねない方法もあるので、注意が必要です。
便は健康のバロメーターなので、毎日便の状態を確認することをおすすめします。便の状態を確認するポイントは、硬さ(形状)・量・色・においの4項目です。快便時の便は、水分を7割〜8割ほど含んでいる、バナナ1本分以上の量である、黄土色または茶色、においが強すぎないことの4つのポイントを満たしています。
便の状態をチェックする習慣を身に付けて、快便生活に役立ててください。
この記事の監修者

宮崎郁子
東京医科大学医学部医学科卒業後、東京医科大学病院 消化器内科、東京医科大学病院 内視鏡センター助教、牧野記念病院 内科を経て、2015年より東京国際クリニック/医科 副院長を務める。
東京国際クリニック

 スキンケア
スキンケア
 オールインワンジェル
オールインワンジェル
 洗顔・クレンジング
洗顔・クレンジング
 化粧水
化粧水
 スペシャルケア
スペシャルケア
 ベースメイク
ベースメイク
 UVケア
UVケア
 ヘアケア
ヘアケア
 メイク
メイク
 ボディ&ヘアケア
ボディ&ヘアケア
 ヘルスケア
ヘルスケア
 美容・健康グッズ
美容・健康グッズ
 暮らしの雑貨
暮らしの雑貨
 すべての商品
すべての商品