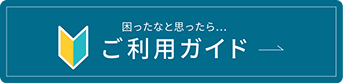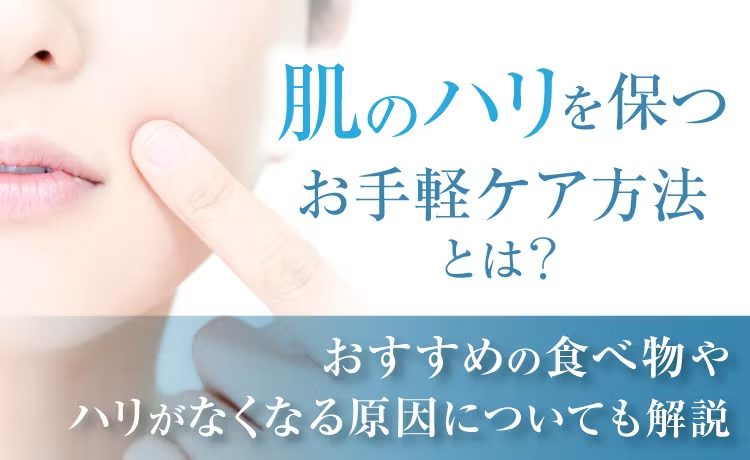コラーゲンは美容・健康によいといわれており、健康食品や化粧品などに広く使用されています。しかし「コラーゲンはそもそも何か」「どんな効果が期待できるのか」など、詳しいことは知らないという方も多いのではないでしょうか。
コラーゲンはタンパク質の一種で、肌や骨などさまざまな部位に存在します。組織の柔軟性や強さのもととなっており、人間の身体に欠かせない栄養素です。
この記事では、コラーゲンの種類や特徴、コラーゲンと一緒に摂取するとよい栄養素、効果的な摂取方法などを詳しく解説します。この記事を読み終えた後、あなた自身が日々の生活の中で上手にコラーゲンを摂取する方法を学び、あなたにとってコラーゲンがとても重要なものだと意識するようになれるでしょう。
コラーゲンとは美容や健康に不可欠な栄養素
体内のコラーゲンの基本的な働き

コラーゲンは、身体の各パーツを構成するタンパク質の一種です。コラーゲンの大部分は細胞の外に存在し、細胞同士を糸のようにつなげ、身体の構造を保つ役割を担っています。
人間の身体の約20%がタンパク質でできており、そのうち30%がコラーゲンです。それぞれの器官でさまざまな役割を果たす、私たちの体に欠かせない成分です。
真皮の70%がコラーゲン!各部位を構成するコラーゲンの割合

コラーゲンは、「肌に存在する成分」というイメージがあるかもしれません。しかし、皮膚だけではなく、血管・髪の毛・内臓・骨・軟骨など身体のさまざまな場所に存在しています。
身体の各部位を構成するコラーゲンの割合は下記の通りです。
・真皮のコラーゲン率:70%
・骨:体積の50%
・関節軟骨:ドライウェイトの60%
コラーゲンは、弾力が必要な肌・血管・軟骨といった部分だけではなく、骨や歯など硬い部分や歯ぐき、目などさまざまな部位で重要な役割を果たしています。
- 骨
- 網の目のような形をしたコラーゲンが丈夫な骨を支えています。
- 歯ぐき
- 歯を支える歯ぐきの成分の約60%がコラーゲンで構成されています。
- 目
- 目を構成する水晶体や角膜にはコラーゲンが含まれています。
上記以外にも、コラーゲンは身体のさまざまな部位の健康に関係しています。
参考文献
※ コラーゲンで、きれいに健康になる!(三笠書房)2004
※ コラーゲンの秘密に迫る(裳華房)1998
※ コラーゲン完全バイブル(幻冬舎)2011
※ 田中栄: グルコサミン研究, 4, 92 (2008)
タンパク質・アミノ酸・コラーゲンの違いは?

タンパク質を構成する一番小さな単位の物質である「アミノ酸」は、自然界では約700種類が発見されています。そのうち、人間の身体をつくるアミノ酸は20種類です。
タンパク質は複数のアミノ酸が結合した物質の総称です。人間の体内では、アミノ酸の組み合わせや全体のつながり方によって、約10万種類ものタンパク質がつくられています。
コラーゲンはタンパク質の一種です。「グリシン」や「アラニン」をはじめとする17種類のアミノ酸によって複雑な「三重らせん構造」をつくっています。
食べ物などに利用されているコラーゲンとしては、「ゼラチン」や「コラーゲンペプチド」があります。「ゼラチン」はコラーゲン分子に熱を加えることで、らせん状を解き、バラバラにした状態です。このゼラチンをさらに小さく分解したものが「コラーゲンペプチド」です。
コラーゲンを食べ物で取り入れる場合、分子サイズや構造によって、吸収されるプロセスなどの性質が異なります。例えばコラーゲンは、たくさんのアミノ酸が連結してできており、体内に入るとバラバラに分解され、アミノ酸の状態で吸収されます。
コラーゲンの種類と特徴
コラーゲンの代表的な種類
人の身体に存在するコラーゲンは、約19種類見つかっており、約30種類のポリペプチド鎖 の組み合わせで種類が決まります。コラーゲンの種類は、Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型…とあらわされます。
- Ⅰ型コラーゲン
- 体内に最も多く存在し、皮膚に含まれるコラーゲンの約8割を占めます。
- Ⅱ型コラーゲン
- 主に軟骨に存在します。
- Ⅲ型コラーゲン
- 血管や子宮などに存在します。

Ⅰ~Ⅴ型コラーゲンの種類を表にまとめました。
| 種類 | 存在する場所 |
|---|---|
| Ⅰ型 | 皮膚の奥にある真皮、骨、じん帯、腱に存在します。 真皮を構成する80%のコラーゲン繊維はⅠ型コラーゲンです。 |
| Ⅱ型 | 主に関節や軟骨に存在します。 また、眼の角膜、硝子体にも含まれています。 |
| Ⅲ型 | 肌や血管、筋肉、腸や子宮などの 内臓に多く含まれます。 |
| Ⅳ型 | 肌の真皮と表皮の間にある「基底膜」に存在します。 |
| Ⅴ型 | 血管・胎盤・筋肉の一種である「平滑筋」に主に存在します。 Ⅰ型、Ⅲ型コラーゲンが存在する組織にも、ごくわずかに含まれています。 |
コラーゲンに共通する構造
コラーゲンにはさまざまな種類がありますが、共通する特徴として、三重らせん構造があります。
コラーゲンは、1,400個以上のアミノ酸でできた長い鎖が3本集まって構成される栄養素です。鎖が互いに巻きつき、らせん状になっています。
裁縫の糸が複数の細い糸を束ねることで強度を高めているのと同じく、三重らせん構造により、コラーゲンに強度と安定性が生まれ、身体の各パーツの構造をつくったり支えたりできると考えられます。

コラーゲンペプチドとは?

食べ物などに含まれるコラーゲンは、分子サイズが大きく、摂取しても消化・吸収されにくいというデメリットがあります。
コラーゲンペプチドは、コラーゲンを加熱したり、酵素などで分解したりすることで、低分子化したものです。分子サイズが小さいため、加工していないコラーゲンと比べ、消化・吸収しやすいというメリットがあります。
かつては口から摂取したコラーゲンペプチドは、消化されるときに分解されアミノ酸になると考えられていました。
しかし、研究により、コラーゲンペプチドのうち一部はアミノ酸に分解されず、そのまま腸に吸収され、血液によって身体全体に届くことが判明しつつあります。
魚由来と豚由来のコラーゲンの違いは?
ドリンク・パウダー・サプリなどの健康食品には、さまざまな種類のコラーゲンが使われています。
コラーゲンは、どの生物に由来するかによって、構造・特徴に違いが生じます。
豚由来のコラーゲンは、人間のコラーゲンと似た構造です。分解・消化がしにくいのがデメリットです。
魚由来のコラーゲンは、養殖されている魚のうろこや天然の魚の皮から抽出され、アミノ酸に分解されやすいのがメリットです。

コラーゲンの合成には鉄分が必要

コラーゲンに特有のアミノ酸である「ヒドロキシプロリン」は、コラーゲンの強い繊維構造に欠かせません。ヒドロキシプロリンを合成するには、特別な酵素の働きが必要です。そして、その酵素が働くには、ビタミンCと鉄分のサポートが不可欠です。
充分な量の鉄分やビタミンCを摂取することで、安定したコラーゲンがつくられます。しかし、食生活の乱れなどによって、コラーゲンの生成に必要な鉄分やビタミンCが不足してしまう可能性があります。
特に女性は、毎月の月経や、過度なダイエットによる偏った食生活によって鉄の摂取量が少なくなるといった理由で、身体の中の鉄分が不足しやすい傾向があります。
ビタミンCや鉄分も積極的に摂るようにしましょう。
コラーゲンの効果的な摂取方法
コラーゲンの吸収について
食事で摂取したコラーゲンはどのようにして吸収されるのでしょうか?
まず、口から体内に入り胃を通過し、小腸に達し消化酵素によって、アミノ酸などに分解されます。コラーゲンの分解によってできたアミノ酸は小腸で吸収され、血液の流れによって肝臓を経由し身体全体に運ばれます。
このように、コラーゲンはそのまま身体に吸収されるのではなく、アミノ酸に分解されてから吸収されます。
健康的な体を維持するため、食事からコラーゲンを摂ることも重要だといえます。

コラーゲンはいつ摂ると効果的?
食事でコラーゲンペプチドを摂取した場合、摂取後およそ1時間で血中濃度のピークに達し、その後も数時間血液中に存在しますが、24時間後の血中濃度は摂取前に近い状態になります。
そのため、コラーゲンは摂るタイミングよりも継続することが重要です。うっかり摂り忘れるのを防ぐためには、コラーゲンを摂る時間を決めておくとよいでしょう。

コラーゲン 1日どれぐらい取ればいい?取り過ぎは良くない?
美容や健康によいとされるコラーゲンの摂取量は、1日あたり5~10g が目安です。しかし、ある調査では20代〜50代の女性の1日あたりのコラーゲン摂取量は、平均1.9gというデータも報告されており、食事だけで摂るのは難しいでしょう。
一般的にコラーゲンが多く含まれているイメージのある食材でも、コラーゲン10gを摂取するには以下の量が必要です。
- 牛スジ(腱・生)
- 約200g
- 鶏もも肉(皮あり)
- 約640g
- さんま(皮つき、生)
- 約550g
食事だけで充分なコラーゲンを摂ろうとすると、食事量が増加し、エネルギー摂取が過剰になる恐れがあります。
食事からコラーゲンを摂るだけではなく、分子が小さく消化・吸収がスムーズなペプチドタイプのコラーゲンを配合したドリンクやサプリメントも活用しましょう。
このように、コラーゲンを摂る際は、量を摂りすぎたり、栄養バランスが崩れたりしないようにすることが大切です。

コラーゲンを豊富に含む食材を紹介
コラーゲンは動物の身体のほぼ全ての部分にあり、タンパク質の総量の3分の1を占めています。 そのため、肉や魚などの動物に由来する「動物性食材」には、コラーゲンが豊富に含まれています。
動物性食材のなかでもコラーゲンを多く含む代表的な食材をご紹介します。食材選びの参考にしてください。

| 食材名 | コラーゲン量(mg/100g) | |
|---|---|---|
| 肉類 | 牛スジ | 4,980 |
| 鶏軟骨(胸) | 4,000 | |
| 豚白モツ | 3,080 | |
| 鶏砂肝 | 2,320 | |
| 豚レバー | 1,800 | |
| 魚介類 | ふかひれ(戻し・湿) | 9,920 |
| ハモ(皮のみ) | 7,660 | |
| うなぎの蒲焼き | 5,530 | |
| サケ(皮あり) | 2,410 | |
| サンマ(皮あり) | 1,820 | |
| 調味料 | スープの素(鶏がら)粉末 | 2,690 |
コラーゲンを食材以外から摂る方法
食材以外からコラーゲンを摂取する主な方法として、ドリンク・パウダー・粒タイプなどの健康食品があります。さまざまな形状のコラーゲンが市販されているので、自分の好みやライフスタイルに合ったタイプを選びましょう。
コラーゲン入りドリンクのなかには、甘みを入れて特徴的な匂いを和らげているものもあります。甘さも様々なので、続けやすい味のものを選びましょう。飽きないようにジュースやスムージーに入れることも方法のひとつです。
パウダータイプは、匂いが少ないものが多く、温かい飲み物や冷たい飲み物に入れる・料理に混ぜるなどアレンジしやすいのがメリットです。
粒タイプは、持ち運びがしやすく、飲みやすいことがメリットです。職場や外出先でも、しっかりコラーゲンを摂取できます。粒が小さく、1回あたりの飲む量が少ないものが便利です。
また、コラーゲンだけではなく他に配合されている栄養素もチェックしましょう。コラーゲンと相性がいい鉄分やビタミンCが配合されているものが良いでしょう。
「ヒアルロン酸」や「プラセンタ」などの美容成分を配合しているものもあるので、目的に合わせて選んでください。

コラーゲンと一緒に摂取するといいものは何ですか?
コラーゲンと相性がいい鉄分やビタミンCを豊富に含む食材を一緒に摂るようにしましょう。
- 鉄分が豊富な食材
- 赤身肉、魚、貝、大豆、小松菜・ほうれん草などの野菜、ひじき・のりなどの海藻類
- ビタミンCが豊富な食材
- レモンなどの柑橘類・アセロラ・キウイフルーツなどの果物、パプリカ・芽キャベツ・ブロッコリーなどの野菜
ビタミンCは水に溶ける性質があり、2~3時間で体外に排出されてしまうので、毎食欠かさずに摂ることが大切です。
ただし、ビタミンCは熱に弱く、加熱すると失われてしまう場合があります。生で食べやすい果物や、加熱処理してもビタミンCが壊れにくいパプリカを食べると、効率的に摂取できます。

まとめ

コラーゲンは、タンパク質の一種で、アミノ酸が結合してできています。人間の身体の約20%がタンパク質で構成されており、そのうち30%がコラーゲンです。
コラーゲンは、肌・骨・髪・内臓など身体のさまざまな場所に存在し、美容や健康に役立っています。
美容や健康に効果が期待できるコラーゲンの摂取量は、1日あたり5〜10gといわれています。しかし、10gのコラーゲンを摂取するためには、鶏もも肉(皮あり)であれば約640gも食べなければいけません。
通常の食事だけでコラーゲンを摂るのは大変だといえます。そこでおすすめなのが、健康食品を上手に活用することです。
コラーゲンを配合した健康食品には、ドリンク・パウダー・粒といったさまざまな形状のものがあります。飲みやすさや匂いの強さ、持ち運びやすさなどの違いがあるので、自分に合ったものを選びましょう。
この記事の監修者

中田早苗
薬科大学卒業後、約7年間病院薬剤師として勤務。
相談薬局へ転職後、食事と生活習慣の見直しから得られる健康に興味を持ち、そのひとつとしてファスティングの魅力に感銘を受ける。
現在は、薬に頼らない体づくりと健康についてSNS(Instagram・TikTok)で積極的に情報発信を行なっている。
Instagram

 スキンケア
スキンケア
 オールインワンジェル
オールインワンジェル
 洗顔・クレンジング
洗顔・クレンジング
 化粧水
化粧水
 スペシャルケア
スペシャルケア
 ベースメイク
ベースメイク
 UVケア
UVケア
 ヘアケア
ヘアケア
 メイク
メイク
 ボディ&ヘアケア
ボディ&ヘアケア
 ヘルスケア
ヘルスケア
 美容・健康グッズ
美容・健康グッズ
 暮らしの雑貨
暮らしの雑貨
 すべての商品
すべての商品